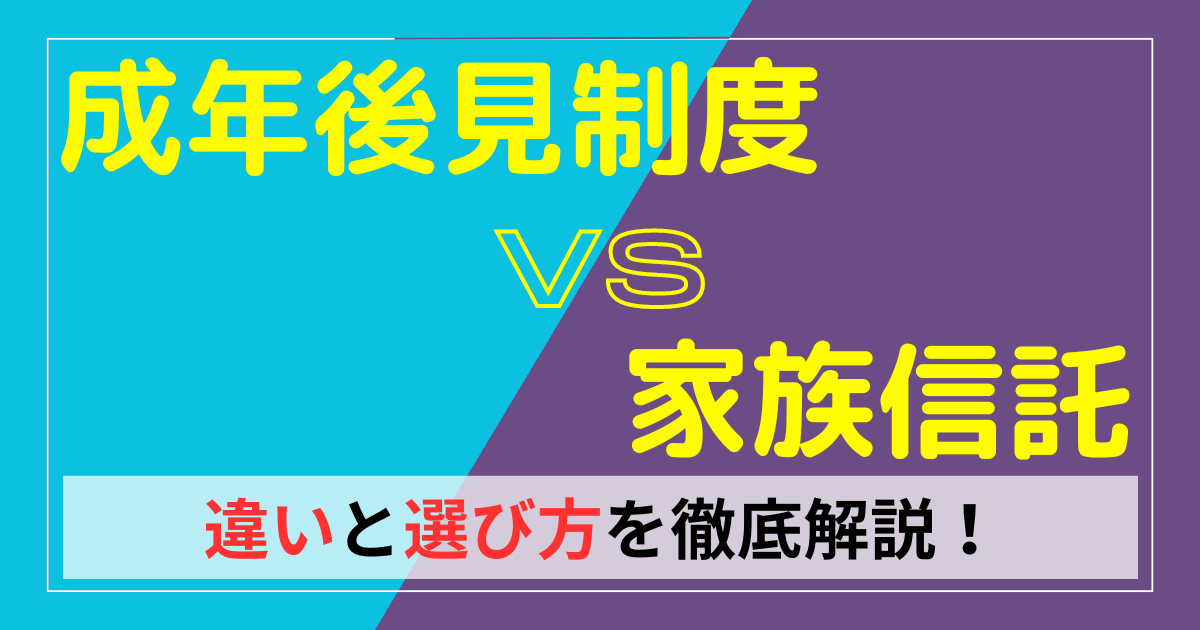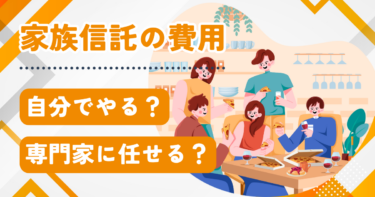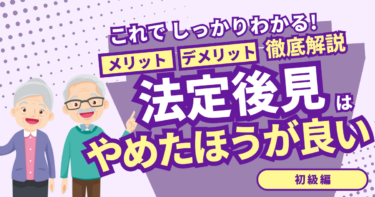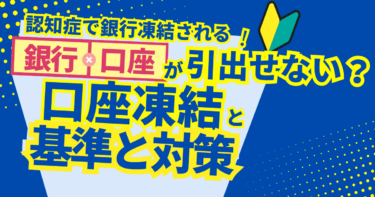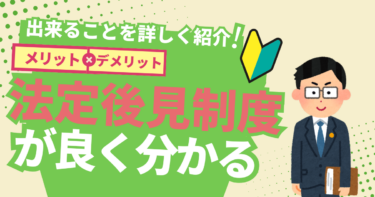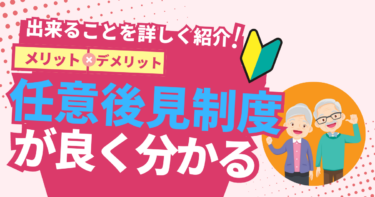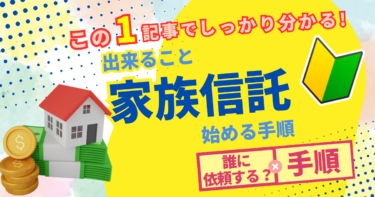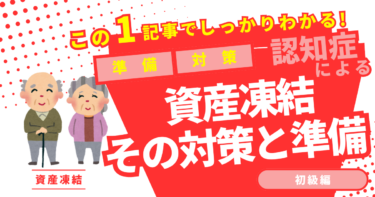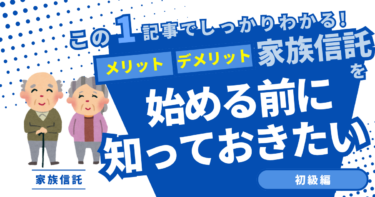![]()
親が認知症になってしまうと、資産凍結という状態に陥ってしまいます。資産凍結を回避するには、どのような方法があるのでしょうか?
この記事では親の認知症からの資産凍結を防ぐために・・・
- どのような方法があるのか?
- 成年後見人のメリット・デメリット
- 家族信託のメリット・デメリット
- 状況別4つの対処方法
について分かりやすく解説していきます。
資産凍結を防ぐ3つの方法
資産凍結とは、財産を持っている本人が認知症などにより「判断能力」を完全に欠いたときに、本人の預金が引き出せない、不動産売却などの契約が出来ない、投資資産を動かせなくなる等、本人の資産が凍結されてしまうことです。
 これを防ぐ方法は、これから説明する3つの方法があります。
これを防ぐ方法は、これから説明する3つの方法があります。
1.法定後見制度とは
「法定後見制度」とは、障害(認知症、知的障害など)により、判断能力が掛けている対象者を保護・支援する制度です。
この制度は家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができる制度です。
| 利用条件 | 本人(親)に判断能力が無いこと |
2.任意後見制度とは
本人(親)に判断能力があるうちに、任意後見人となる人や将来委任したい事務内容を公正証書による契約で定め、本人(親)の判断能力が不十分となった時点で、選任された任意後見人が本人に変わって行う制度をいいます。
| 利用条件 | 本人(親)に判断能力があること |
3.家族信託とは何か
本人(親)の保有する財産を、自分の老後の生活や介護費用等の管理を目的として、保有する預貯金・不動産等の資産を信頼できる家族に託して管理・処分を任せる仕組みを言います。
家族や親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません
| 利用条件 | 本人(親)に判断能力があること |

そこに「家族信託」を入れて3つの方法があります!
3つの制度を徹底比較
これから説明の中で「身上監護」という、聞き慣れない言葉が現れますので、はじめに解説しておきます。
「しんじょうかんご」と読みます。成年後見制度において対象者(親)の暮らしの維持を目的とし、成年後見人が対象者の代わりとなって、生活、医療、介護などの契約手続きを進める法律行為をいいます。
ただし身上監護には、実際に生活する上での支援行為は含まれていません。あくまで法律上の行為のみを指します。
出来ること、出来ないことを比較
まずは、それぞれの「できる事」から見てみます。
| ⭕出来る | |
| 法定後見 | ✅身上監護(取消権あり) ✅財産管理 |
| 任意後見 | ✅身上監護(取消権なし) ✅財産管理 |
| 家族信託 | ✅財産管理 ✅遺言代用 ✅事業承継 ✅相続対策 |
つぎに、それぞれの制度の「できない事」を比較しましょう。
| ❌出来ない | |
| 法定後見 | ⛔財産管理は被後見人を不利益から守るための必要最低限のみ |
| 任意後見 | ⛔財産管理は被後見人を不利益から守るための必要最低限のみ ⛔取消権がないので被後見人の行為を取り消せない |
| 家族信託 | ⛔身上監護ができない |
利用するための条件の比較
それぞれの制度を利用するには条件が必要です。
| 利用条件 | |
| 法定後見 | ✅被後見人(親)の判断能力が無いこと |
| 任意後見 | ✅被後見人(親)の判断能力があること |
| 家族信託 | ✅被後見人(親)の判断能力があること |
メリットとデメリットを比較
それぞれの制度のメリットとデメリットを比較します。
| メッリット・デメリット | |
| 法定後見 | 【メッリット】 ✅財産管理も身上監護もどちらも出来る ✅判断能力が無い場合の最後の手段 |
| 【デメリット】 ⛔後見人の選任、職務内容までほとんど自由が利かない ⛔すべてに後見人と家庭裁判所が関与し自由が利かない | |
| 任意後見 | 【メッリット】 ✅財産管理と身上監護どちらもできる ✅後見人、後見内容を自由に決めることができる |
| 【デメリット】 ⛔財産管理は本人の不利益を避けるための最低限の財産管理しかできない ⛔被後見人(親)の判断能力が無い場合には利用できない | |
| 家族信託 | 【メッリット】 ✅財産管理は自由に運営できる ✅本人(親)が亡くなった後の資産承継等についても設定できる |
| 【デメリット】 ⛔身上監護ができない ⛔被後見人(親)の判断能力が無い場合には利用できない | |
制度の終了期限の比較
| 終了期限 | |
| 法定後見 | ✅被後見人の判断能力の回復または死亡するまでは制度利用をやめることができない |
| 任意後見 | ✅任意後見開始前ならいつでも契約解除ができる ✅任意後見開始後は、相当の理由がある場合に限りは契約解除できる |
| 家族信託 | ✅契約時に信託終了事由を定めておけば、信託を終了することができる ✅委託者と受益者の合意があれば終了できる |
変更や解任制度の比較
| 変更・解任 | |
| 法定後見 | ✅法定後見人が違法行為等をした場合に限り、解任することができるが、基本的には変更はできない |
| 任意後見 | ✅後見開始前であれば契約を解除、新たな後見人と再度任意後見契約を結ぶことができる ✅後見開始後はいったん任意後見を終了し、法定後見に移行する必要があるため、任意の相手を再度後見人にすることはできない |
| 家族信託 | ✅契約時に変更事由を定めておく事で変更することが可能 ✅変更事由の定めがない場合は、委託者と受益者の合意があれば変更できる |
費用の比較
各制度とも、初期費用、継続費用、その他書類作成費用などが掛かります。ここではごく平均的な費用を比較します。
| 費用比較 | |
| 法定後見 | ✅初期費用が約10〜30万円(財産額や専門家により異なる) ✅継続費用は月額0〜約10万円 |
| 任意後見 | ✅初期費用が約10万円〜150万円(財産額や専門家により異なる) ✅継続費用は月額0〜約10万円 |
| 家族信託 | ✅初期費用が約5万円〜150万円(財産額等により異なる) ✅継続費用は月額数千円~数万円 |
状況別の4つの対処方法
1.判断能力を既に失っている場合
親の認知症が進み「判断能力を完全に欠いてしまった状態」であれば、選択肢は「法定後見制度」のみとなります。法定後見制度では全く見ず知らずの職業後見人が選任される事が多く、身上監護、財産管理ともに、かなり制限されますので、出来ればおすすめしたくない選択肢ですが、判断能力がなければこの制度に頼るほかはなくなります。
まだ判断能力がある場合の2つの選択肢
2.任意後見制度(身上監護を優先したい)
親がまだ健在である。または軽度の認知症が進み始めている段階であれば、高い確率で「任意後見制度」を利用できます。任意後見制度は「身上監護」もできるし、限定的ではありますが「財産管理」も出来るので、判断能力がある限り法定ではなく、こちらの任意後見制度を利用するほうが良いでしょう。
3.家族信託(財産管理を優先したい)
法定後見、任意後見ともに「財務管理」がありますが、あくまで被後見人(親)の不利益にならないよう、できるだけその財産を守ることを目的としていますから、かなり限定的な管理しかできません。
それに比べて、家族信託の「財産管理」は自由度が高く、管理できる財産の種類(預貯金、不動産、事業継承、相続対策など)が多く、依頼者(親)の望む財産の使い方ができるので、財務管理を中心に考えるのであれば、まちがいなく家族信託を選ぶべきです。
ただし家族信託は、身上監護はできません。
4・理想はハイブリッド方式?
本人(親)の判断能力があるなら・・・
- 任意後見制度の「身上監護」の部分を取り
- 家族信託の「自由度の高い財産管理」を取る
出来れば、このハイブリッド型で「いいとこ取り」するのが、もっとも自由に管理ができる完全版です。
| 身上監護 | 財産管理 | |
| 任意後見の長所 | ⭕できる | 限定的 |
| 家族信託の長所 | ⭕自由な財産管理ができる | |
| ハイブリッド | ⭕身上監護ができる | ⭕自由な財産管理ができる |
ご両親が高齢となってきたら、認知症で判断能力を失う前に、ハイブリッド型でご両親の財産を守ってください。

「任意後見」と「家族信託」のハイブリッドで
完璧に管理したいですね!
まとめ
親が認知症になってしまうと資産が凍結され、親名義のすべての資産が動かせなくなってしまいます。
これを防いで、親本人が望む形の老後の財産管理をするためには、認知症になる前に「任意後見制度」または「家族信託」を組成することが重要です。
法定後見制度は親本人の判断能力がすでに無い場合の、やむを得ない最後の手段ですから、まだ症状がでていない内に任意後見人、家族信託、またはハイブリッドでその両方を同時進行することをおすすめします。