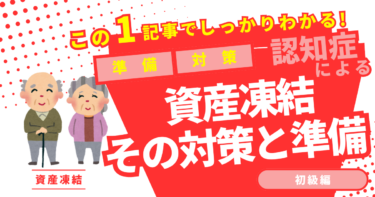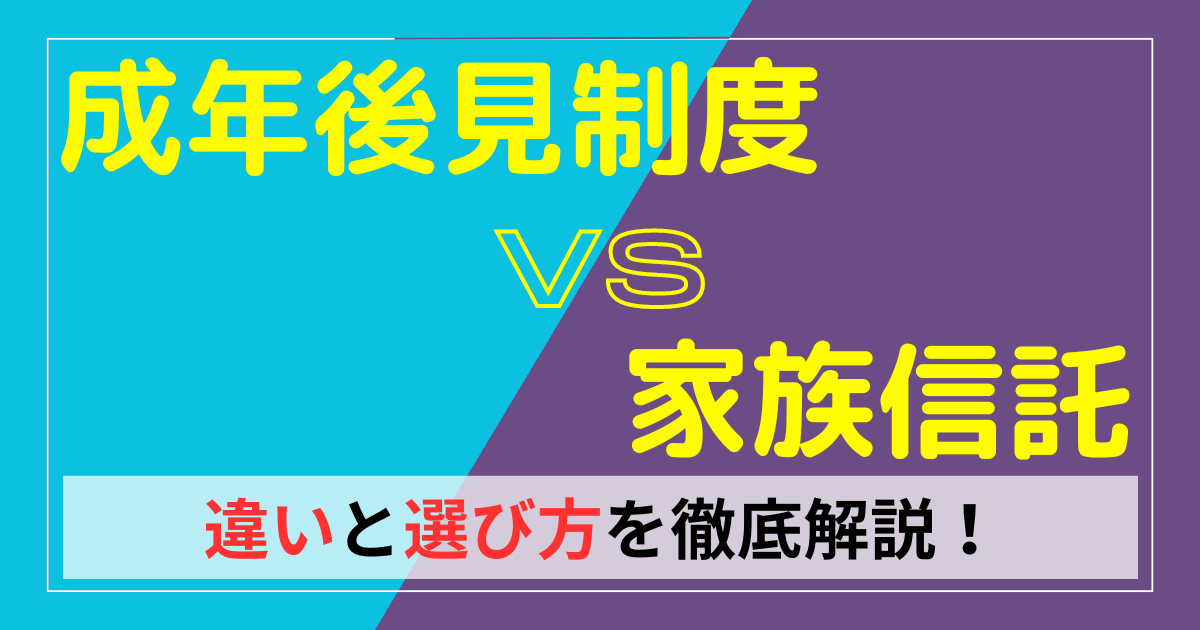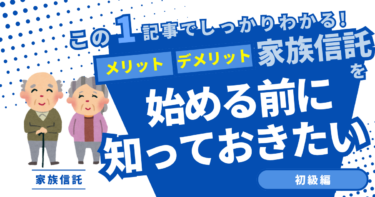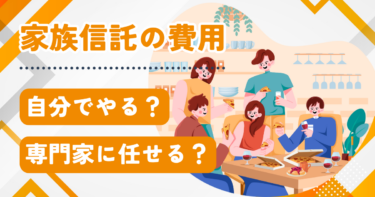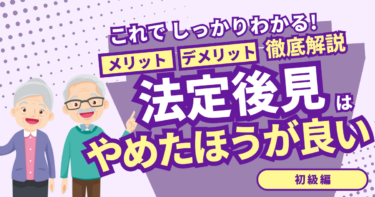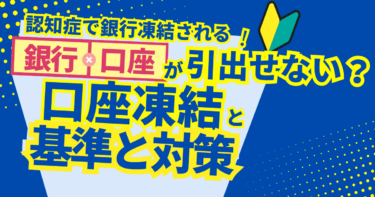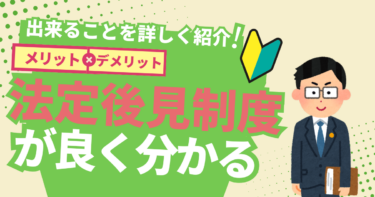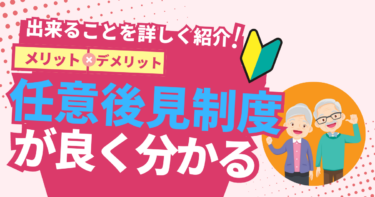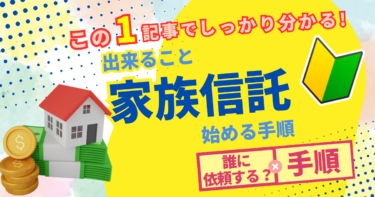![]()
ログライン
この記事では
- 親の認知症による資産凍結とは何か?
- 銀行口座はいつ凍結されるか?
- すでに認知症ならどうするか?
- 認知症になる前にできる予防対策
について解説していきます。
認知症による資産凍結とは
認知症と診断されると「著しく判断能力や意思能力が低下している」とみなされ、法律行為の全般が出来なくなります。
どのような法律行為かというと
- 預貯金国座の引出し、解約
- 不動産売買や賃貸契約
- 資産運用商品の売買や処分
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 生命保険の加入、保険金の請求・受取
- 相続手続き(遺産分割協議、相続放棄など)
このように認知症になると、自分の財産なのに思うように使えずに「凍結」されてしまいます。
銀行口座はいつ凍結される?
認知症になったからと言っても銀行にバレなければ、カードでの引落し、スマホアプリでの振込、自動引き落としなどは、引き続き使用はできます。
しかし、新しい銀行カードを発行したいときや、定期預金の解約など、銀行の窓口に本人が直接手続きをしなければならない時に、行員とのやりとりで発覚することがほとんどです。
本人が銀行に行かなければ、しばらくは誤魔化せますが、それでもいずれバレてしまいます。銀行口座が凍結されてしまうのは、その時です。また凍結されてしまうと、代理カードも使えなりますから注意が必要です。
すでに認知症ならどうするか
本人(親)がすでに認知症と診断されている場合、家族信託や任意後見制度は使えません。唯一使える制度は「法定後見制度」のみとなります。
法定後見制度で後見人を選任すれば、凍結された本人の資産を動かすことが出来るようになります。
後見人には家族も立候補することは出来ますが、最終的には家庭裁判所が決定します。最近の傾向では、家族が立候補したとしても家裁が選ぶのは9割が弁護士や司法書士という結果がでています。つまり、会ったこともない見ず知らずの第三者が親の財産の管理人となるわけですから、親の希望や、家族の意見を通すことはかなり難しくなります。
「法定後見制度を利用して後悔している」という声が多いのはこのためです。しかし、認知症になってしまったら、残念ながらこの方法しか資産凍結に対処できる制度はありません。
法定後見制度の詳細は別記事でご紹介していますので、そちらもお読みください。
親が認知症になってしまうと、資産凍結という状態に陥ってしまいます。資産凍結を回避するには、どのような方法があるのでしょうか? この記事では親の認知症からの資産凍結を防ぐために・・・ どのような方法があるのか? […]
親が元気な今のうち(判断能力ある今)なら、もっと自由度の高い制度を利用することが出来ますから、今から前もって準備を始めるのが得策です。

自由度の高い「任意後見制度」や「家族信託」
といった制度を利用することができます
認知症になる前にできる予防対策は
認知症になる前は、親は当然「元気」ですから何の問題もない状態です。そんな親との関係の中で「お父(母)さんが認知症になる前に、今ある財産を子供に託す『家族信託』を作ろうよ」とはなかなか切り出せないものです。
しかし、どんどん高齢に向かっていくわけですから、必ず認知症や動けなくなる時期がやってきます。すでに説明をしましたが、完全に判断能力が無くなってしまうと、資産凍結を解除する方法は「法定後見制度」のみとなります。
認知症になる前であれば、より使いやすい2つの制度がありますから、そのどちらかの制度の利用を今から準備しましょう。
認知症前なら『任意後見制度』
任意後見制度とは、財産を委託する本人(委託者)の判断能力が十分なうちに、家族や親族等の中から後見人(受託者)を選び、将来自分が認知症などで判断能力が不十分になったときに、支援を受ける制度です。
契約内容はある程度自由に決めることが出来、自分の判断能力が低下した後の財産管理、身上監護(生活、望む介護等)についての具体的なライフプランを決めていきます。
任意後見制度の代理権は「財産管理」と「身上監護(しんじょうかんご)」の2項目です。
この任意後見契約の効力は、判断能力が不十分になるまでは発動せず、本人の判断能力が低下した時から始まります。
任意後見制度の財産管理
基本的には本人名義の財産を管理することになります。本人の希望する暮らしを実現するために、契約書でお金の使い方を細かくきめていきます。
ただ、財産管理が後見人の思い通りに出来るわけではなく、実家(不動産)の売却など、家庭裁判所の承認が必要になってきます。さらに、後見人が問題のある管理をしないために、家裁から「監督人」が付き管理していきます。
任意後見制度の身上監護(しんじょうかんご)
身上監護(しんじょうかんご)とは聞き慣れない言葉ですが、親の暮らしの維持を目的としたもので、生活・医療・介護などの「契約手続き」を進める法律行為を言います。身上監護の目的はあくまで親の生活の支援を目的とするものであって、後見人が管理をするものではありません。任意後見制度を組成する時に、親の意志をしっかりと確認することが重要です。
なお、身上監護(身上保護とも言う)は、実際の暮らしを支援するような行為(実際の介護業務、食事の世話など)は含まれません。あくまでも、契約などの法律行為のみを指します。
認知症前に最も使い勝手の良い制度が『家族信託』
家族信託を簡単に説明すると、親本人の財産を信頼できる家族や親族に託し、老後の生活や介護などのために資産の一部または全部の管理や処分任せ、財産を与えたい人(自分も含む)に給付や継承する仕組みを言います。
家族信託では家庭裁判所などの関与もないために、もし将来、生活費などの預貯金が足りなくなったりした場合に、受託者が自宅を処分売却することも出来ます。裁判所の承認は必要ありません。
財産管理の面で、成年後見制度(法定後見制度、任意後見制度)と比べ、自由に采配できるために、今とても注目されている制度です。
家族信託にもデメリットがある
そんな財産管理が自由にできる家族信託ですが、デメリットもあります。
それは成年後見制度にある「身上監護」が無いことです。成年後見制度では法律上、身上監護として依頼者(親)の医療や介護の契約行為が義務付けられていますが、それは家族信託にはありませんから、受託者や周りの家族の気遣いでカバーする形となります。

親と家族の”意志”を自由に実現できる
「家族信託」に優る制度は他にありません!
親が認知症により資産凍結をされないための、財産管理が非常にし易い『家族信託』ですが、締結する前にそのメリットとデメリットを知っておく必要があります。 この記事では・・・ 家族信託とは何か 家族信託のメリットとデ[…]
まとめ
以上、親の資産凍結を解決していく方法を説明してきました。
親がすでに認知症などで「判断能力」が無い場合には、法定後見制度で解決することが出来ます。
ただ理想的には、親が判断能力を失う前に、親と家族で家族会議を開き・・・
- 任意後見制度
- 家族信託
どちらの制度が自分たちの場合に合っているかを、十分検討し話し合うことをおすすめします。親の資産を守るためには、「親」と「子」がしっかりと連携するのが一番です。