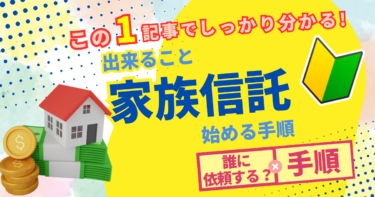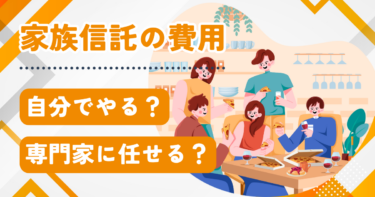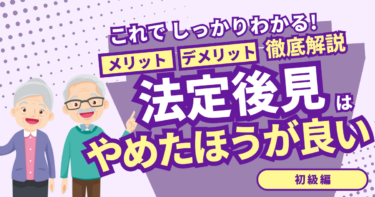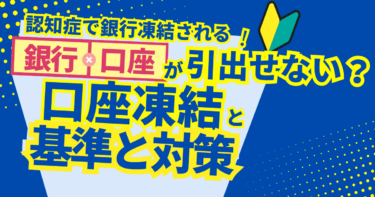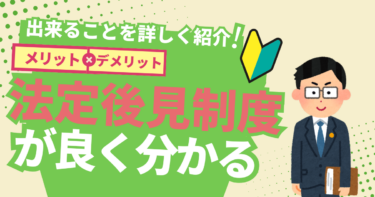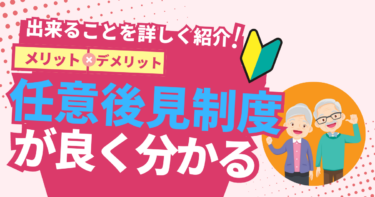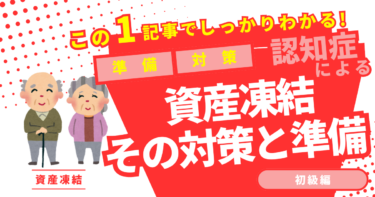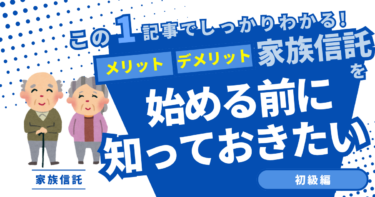![]()
親の認知症による資産凍結から財産を守る方法は3通りあります。その中でも家族信託は使い勝手がよく、いま注目されている親の資産管理の制度です。
この記事では、その家族信託が・・・
- なぜ今、家族信託が注目されるのか
- 家族信託で出来ることとは?
- 家族信託は自分で作れるのか?
について解説していきます。
家族信託とは
家族信託は、親の財産を資産凍結から守るため、その財産を家族に託して管理や処分を任せる事ができる制度です。
家族信託を活用すれば、将来親が認知症などで判断能力を失ってしまった際の資産凍結を防ぐことが出来ます。
簡単に言えば・・・
親(委託者)が自分の財産の管理・処分する権利を、家族(受託者)に任せて指示した通り(契約内容)に仕事をしてもらう。そして、自分やその財産を分け与えたい人(受益者)に生活費を支給したり、財産を相続していく仕組みになっています。
このように家族信託には「委託者」「受託者」そして「受益者」の3者の契約活動をいいます。これにより、財産所有者である親が認知症などの影響を受けずに、子どもや配偶者などが信託された財産の管理運用処分ができるようになっています。

成年後見制度と同様、親の認知症からの資産凍結を解決するための制度の1つですが、家族信託が一番本人(委託者)の意向を反映してくれる制度のために、いま家族信託に注目が集まっています。
家族信託でできること
家族信託は親の財産を、委託された家族が管理・処分をする制度で、以下のような事ができます。
- 本人が元気なうちから財産の管理・処分を進める事ができる
- 将来、認知症などで本人の判断能力が低下した後の財産管理対策ができる
- 障がいがある子どもの生活保障対策を行うことができる
- 成年後見制度よりも柔軟性が高い財産管理を行える
- 本人死亡後の資産継承先を指定できる(相続)
- 二次相続以降の資産継承先の指定(受益者連続信託)ができる
- 円滑な事業承継を行う事ができる
似たような制度に成年後見制度がありますが、家族信託はより自由度が高く、しかも幅の広い財産管理ができる特徴を持ちっています。
家族信託を始める手順
家族信託を始めるには、以下の2通りの方法があります。
- すべて自分でやる場合
- 専門家に依頼する場合
家族信託を自分で作る流れ
家族信託を自分で作成する手続きは以下のような流れになります。
- 事前準備
- 信託契約書の作成と締結
- 信託財産の移転
- 信託開始
事前準備
家族信託とは、親(委託者)の希望通りに委託者の所有する財産を、管理・運営していく契約行為です。そのためには、まず親(委託者)と家族が同席して、信頼できる財産管理を任せるための受託者(通常は子ども)を決める必要があります。
その後、委託者と受託者の間で、信託財産目録を作成し、その管理ルールを決める必要があります。
- 家族信託の目的を明確化する
- 信頼できる受託者を探す
- 信託財産と管理ルールを決める
この家族信託の目的を決める事が、ファーストステップとなります。
信託契約書の作成と締結
委託者、受託者、受益者が決まり、信託目的が決まれば、次は信託契約書に記載すべき事項を列挙し、落とし込んでいく作業となります。
信託契約は公正証書で行ったほうが無難でしょう。ここで公証人という法律のプロがチェックをしてくれます。ただ税金面などのチェックはしてくれません。
必要書類は・・・
公正証書作成時の必要書類
信託契約書が出来たら、それを公証役場で公正証書を作成する必要があります。
- 住民票
- 印鑑証明書
- 実印
- 本人確認のための身分
等が必要になります。
不動産の信託登記の必要書類
委託者(親)の所有する不動産を信託登記をする作業に入ります。
- 不動産の権利証や印鑑証明書
- 実印
- 住民票
- 固定資産税の評価証明書
等が必要になります。
信託口座開設の必要書類
委託者(親)の財産を管理するためには、家族信託専用の信託口座を開設する必要があります。受託者(子ども)にとって「人の財産」ですから、口座はきちんと分けて管理する必要があります。
- 締結済みの信託契約書
- 本人確認のための身分証
- 銀行印
等が必要になります。
信託財産の移転
必要書類が整い次第、預貯金などは家族信託用の信託口座へ、不動産は所有権移転登記を始めます。これらの手続きは子どもや配偶者が単独で行うことは出来ないので、必ず委託者本人が手続きをする必要があります。
特に不動産の信託には、信託目録を作成し法務局へ提出します。
信託開始
以上の作業が終了したら、いよいよ信託が開始し、受託者による管理が始まります。
不動産の場合には所有権移転登記の作業だけに終わらず、火災保険などの変更も必要です。さらに、管理する不動産が賃貸不動産である場合には、入居者への通知も必要になります。
税務署へは信託の計算書を毎年提出する義務がありますので、信託開始と同時に税務署に確認しましょう。
費用
自分で手続をする場合、最低でも以下の費用は掛かります。
- 印紙税(200円)
- 公正証書の作成費用(財産総額で異なり5~10万円程度が目安)
- 不動産の信託登記の登録免許税(土地・建物に課税)
- 信託口座開設手数料(銀行により異なる|5000~10万円程度)
おおよその目安として、このようになります。財産の総額によって大きく金額が異なります。
自分で家族信託を作るメリット・デメリット
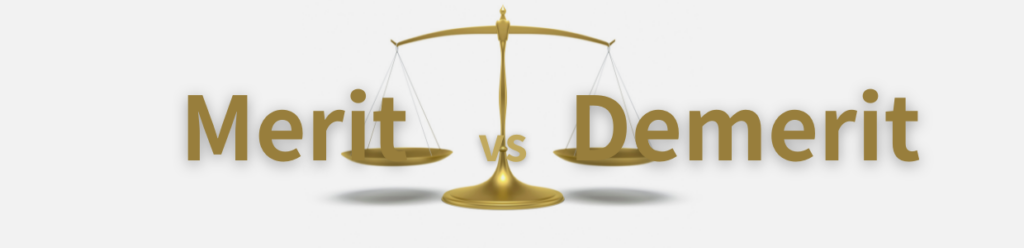 メリット
メリット
自分で家族信託を作るメリットは、なんと言っても「費用が安く収まる」ことです。弁護士・司法書士などの専門家に掛かるコンサルティング料や契約書の制作費用が掛かりません。
通常、専門家に依頼すると数十万円~数百万円の報酬が発生します。おおよその目安として、信託財産の1%以上は見積もる必要があるでしょう。自分で作成できれば、この大きな費用が節約できます。
家族信託の仕組み、契約書を作る知識・技術がある人におすすめの方法です。
デメリット
家族信託を自分で組成する場合、次のような事柄が起こる可能性が高くなります。
- 内容の詰めが不十分になり後から問題が生じる
- 信託契約に不備が生じる可能性がある
- 家族間なので合意を得にくい場合が多い
- 故人で作った信託契約だと銀行から断られる場合もある
- 他にもっと適した制度があったかもしれない
自分で家族信託を組成する場合、すべての協議が家族間となるために、利害関係も生じて話がまとまらない場合が多いです。
また銀行で信託口座を開設する際に、銀行によっては「個人が作成した契約書だから」と断られるケースもあります。もっと根本的に、第三者が協議に入らないために「実はもっと良い制度があった」なども考えられます。
家族信託を自分で作れば、組成費用は大幅に節約出来ますが、第三者が間に入らない事で、これらのようなデメリットが生じる場合もあります。自分で作成する場合には、よく熟考することが重要です。
専門家に依頼する場合
家族信託を自分で作れる知識・技術を持っていれば良いですが、ちょっと法律知識がある程度の方は、やはり専門家に頼むのが得策でしょう。自分で組成したために後々問題が発覚して、その対処に余計に費用も時間も掛かってしまったら、元も子もありません。
それでは専門家に依頼する場合、弁護士や司法書士なら誰でも良いのかというと、そうではありません。
弁護士や司法書士にも「専門分野」がありますから
「家族信託に精通した専門家」に依頼するのが正解です。
ただ1つだけ注意したい点は、家族信託の組成が終わると、依頼はそこで終了し、その後のアフターフォローは基本ありません。もちろん依頼した弁護士・司法書士に聞けば教えてくれるでしょうが、その都度「顧問料」が発生します。
まとめ
親が認知症等の判断能力欠如による資産凍結のリスクから守るための制度に家族信託があります。家族信託は、最近特に利用者が増えている、資産凍結を解決する3つの制度の中の1つです。
家族信託は自分で作る事も可能で、上記にその概要をまとめました。しかしながら、自分で作る際のデメリットが意外と大きいため、よほど家族信託の仕組みや契約知識に強い人で無い限りおすすめは出来ません。
通常は専門家に任せます。専門家であればリスクを最小限に抑えることができるので、一般の人には専門家依頼がおすすめです。
ここで朗報ですが・・・
地元の弁護士・司法書士ではなくても、家族信託は作れます。それが今テレビCMでも話題の『おやとこ』という会社です。『おやとこ』は家族信託を専門に組成する会社で、その営業母体はトリニティ・テクノロジー㈱という士業の会社です。
このトリニティ・テクノロジー㈱は、参加に弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人をグループ企業とする、大手の士業です。特に『おやとこ』という屋号で活動している家族信託に特化したサービスでは、他専門家には追随できない・・・
- 家族信託の組成費用を価格破壊を実現したリーズナブル費用
- 日本中どこでも家族信託が作れる「全国ネット」
- 激安価格でアフターフォローできるアプリが使える
以下から企業詳細ページ、公式ページを確認できます。